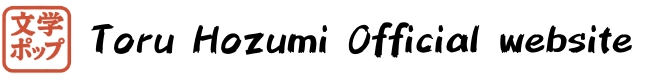本は、「読む」より「触れる」でもいい
「本を読む」と聞くと、全部理解しなきゃいけない、内容を頭に入れなきゃいけない、と思っていませんか?
特に近代文学なんて、古い言葉や知らない時代背景が出てきて、最後まで読んでも「結局よくわからなかった…」ということも多いはずです。
でも、それでいいんです。
本は、テストのために暗記するためのものじゃありません。
山や川を見て「きれいだな」と思う感覚と同じように、本も“感じる”ものでいい。
たとえば、小説の中にたった一行、ハッとするようなきれいな日本語を見つけたら、それだけで読む価値があります。
一文だけ心に残ったなら、その本はもうあなたの一部になっています。
近代文学には、今の私たちが普段使わない言葉や、想像もつかない風景がたくさん出てきます。
最初から全部を理解しようとすると疲れてしまうけれど、「知らないものに触れる」こと自体がもう意味のある時間です。
ページをめくるたびに、景色を眺めるような気持ちで楽しめばいいんです。
だから、あなたも「読む」というより「触れる」つもりで、本と向き合ってみてください。
意味がわからないままでも、好きな言葉やフレーズを見つけたら、それがあなたと本との出会いです。
それだけで、本はもうあなたに何かを届けています。

本を読むのは筋トレと同じ
本を読むのは、筋トレとよく似ています。
初めてダンベルを持ったとき、重くて持ち上がらないのは当たり前ですよね。
それと同じで、本も最初はなかなか読めなくて当然なんです。
特に、文学ポップで扱うような近代文学は、いきなり初心者が挑戦するにはハードルが高く、読書が嫌いになるかもしれません…。
難しい言葉、昔の生活や文化の描写、長い文章…これらは、読み慣れていない人にとっては「重いダンベル」みたいなもの。
だから、最初に原作を読んで「全然理解できない…」と思っても、落ち込む必要はまったくありません。
むしろ、それが普通です。
もし近代文学が難しすぎると感じたら、本屋に行ってみてください。
店員さんがおすすめしている人気の小説や、平積みになっている話題作を手に取って、少し中を読んでみる。
「これなら何とか読めそうかも」と思えたら、それが今のあなたにとってちょうどいい一冊です。小説がきつそうと思ったのであれば、短編が多く入った本や、詩集でも良いかもしれません。
ここで大切なのは、決して「理解できない自分を責めない」こと。
読書習慣が少ない現代では、最初からスラスラ読める人のほうが珍しいんです。
少しずつ読み続ければ、必ず読む力はついていきます。
だから、最初は軽いダンベルから始めるように、自分に合った本から読めばいい。
それが、読書を長く続けるためのコツです。

読書で得られるもの
「本なんて読まなくても、ネットや動画で情報は手に入るじゃない?」
そう思う人も多いかもしれません。確かに、スマホを開けば世界中の情報がすぐ届く時代です。
でも、読書にはネットや動画では得られない価値があります。
また、コスパやタイパを追い求める風潮に疲れを感じている人も多いのではないでしょうか。そうした流行はやがて終わりを迎え、これからは一つの物や出来事に深く向き合い、時間をかけてじっくり味わう時代へと移っていくと思います。
1. 他人の人生を生きられる
小説を読むことは、自分では経験できない人生を追体験することにつながります。登場人物の感情や葛藤に入り込むことで、世界の見え方が大きく変わります。例えば、旅先で目にした何気ない風景が「あの小説の場面みたいだな」と感じられたり、「あの登場人物ならこの景色をどう思うだろう」と想像できたりします。さらに、現実の人間関係においても、他人の優しさや地道な行動に心を動かされるようになるのです。この感覚は文章では伝えきれません。ぜひ、実際に体験していただきたいと思います。
2. 創作力や美意識が自然と身につく
読書は、創作をする人にとって最高のトレーニングになります。小説の中では、キャラクターの感情や場面の雰囲気が細かい言葉で描かれています。その描写に触れることで「こんな表現をすれば、もっと伝わるんだ」と気づけます。これは、イラストでキャラの表情を描くときや、漫画でコマ割りを工夫するとき、歌詞や台本を書くときにも役立ちます。
また、本に出てくる比喩やきれいな言葉に触れると、普段の景色や何気ないしぐさにも「これって作品に使えそう」と感じるようになります。こうした感覚が、美意識を育てて、自分の絵や歌や動画をより「エモい」作品にしてくれるのです。
3. 集中と内省の時間になる
現代は情報が細切れに流れていく時代です。そんな中で本を読む時間は、一つの物語やテーマにじっくり向き合える貴重で贅沢な機会です。そこから思考の深さが培われます。本は文字だけで世界を描くため、言葉の使い方や考えの組み立て方を自然に学ぶことができます。その結果、自分の意見を明確に伝える力も磨かれていきます。(実際、著名人に読書家が多いのも無関係ではないでしょう)
本を読むことは、単なる知識のためではありません。
それは「時間をどう生きるか」を選ぶ行為であり、人生を豊かにするひとつの方法なのです。